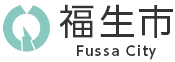介護保険料
介護保険料について掲載しています。
介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直されます。市では今後の介護サービスにかかる費用などを推計し、令和6年度から令和8年度までの介護保険料の基準額を6,176円(月額)と設定しました。この基準額をもとに所得に応じた負担となるように18段階に設定されます。基準額と段階数は市町村ごとに決められています。
介護保険料賦課の根拠について
- 介護保険法第129条(保険料)及び福生市介護保険条例により、賦課期日(4月1日)において福生市の第1号被保険者(65歳以上)の方に賦課されます。ただし賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得された方は、資格を取得された月からの月割りで算定した額が賦課され、資格を喪失された方は、資格を喪失された月の前月までの月割りで算定した額が賦課されます。
- 納付義務者は、福生市内に住所を有する65歳以上の方及び住所地特例者です。
- 保険料の金額は、福生市介護保険条例第4条の規定によります。個別の保険料額等については、毎年7月に送付される「介護保険料納入通知書」または「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」をご覧ください。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から差し引く特別徴収と、納付書で納める普通徴収の2通りがあります。
- 特別徴収の場合
老齢基礎年金・厚生年金などの退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方が該当します。特に手続きの必要はありません。
特別徴収の方は、市から保険料額決定通知書が届きます。 - 普通徴収の場合
老齢基礎年金・厚生年金などの退職年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の方や、年度の途中で65歳になられた場合、年度の途中で他市町村から転入した場合などは、市から送付される納付書に基づき、納めていただきます。
普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用いただきますと、納め忘れなどがなく便利です。
保険料の改定について
介護保険は3年に一度、「介護保険事業計画」を策定し、適正な運用に努めております。
この計画に基づき介護保険料の見直しが行われ、第9期計画(令和6年度から令和8年度)の介護保険料は、介護サービスに係る費用などを推計し、次のとおり決定いたしました。
所得段階別の介護保険料一覧表(第9期介護保険事業計画)
介護保険法施行令の一部改正により、令和7年度から、第1段階、第2段階、第4段階、第5段階の保険料の算定基準額が変わりました。
令和6年度まで、老齢基礎年金(満額)79万4,500円の支給額相当として「年金収入等80万円」が基準とされていましたが、令和6年1月から12月の老齢基礎年金(満額)の支給額が80万9,000円となったことから、令和7年4月から「年金収入等80万円」の基準が「年金収入等80万9,000円」に改正されました。
【改正前】令和6年度
| 所得段階 | 対象となる方 |
|---|---|
| 第1段階 |
次のいずれかに該当する方 ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円以下の方 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円超120万円以下の方 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円以下の方 |
| 第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円超の方 |
【改正後】令和7年度・令和8年度
| 所得段階 | 対象となる方 |
|---|---|
|
第1段階
|
次のいずれかに該当する方 ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円以下の方 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円超120万円以下の方 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円以下の方 |
| 第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円超の方 |
保険料に係る特例措置の廃止
第8期の保険料では、平成30年の税制改正の影響を避けるため、市民税課税者(保険料段階第6段階以上)のうち、合計所得金額に給与所得または年金所得が含まれている場合、10万円を控除した金額を所得指標としていましたが、第9期からは10万円の控除がなくなります。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)
40歳以上64歳以下の方の保険料は、その方が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険税(料)と合算して納めます。
医療保険が国民健康保険の場合、国民健康保険税の中に介護保険分が合算され、原則として半分を国が負担し、世帯主が世帯主及び世帯員の分を負担します。
職場の健康保険、共済組合に加入している方の保険料は給与に応じて異なり、原則として半分を事業主が負担します。また、被扶養者の方は、個別に保険料を納めることはありません。
第2号被保険者の方の保険料は、給与明細書や国民健康保険税納税通知書などでご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764